LSO/ティッチアーティ/ヴェンゲーロフ(vn):女王陛下に大接近 ― 2012/12/05 23:59
2012.12.05 Barbican Hall (London)
Robin Ticciati / London Symphony Orchestra
Timothy Redmond (conductor-1)
Maxim Vengerov (violin-2)
1. Maxwell Davies: Fanfare - Her Majesty's Welcome (LSO commission)
2. Tchaikovsky: Violin Concerto
3. Elgar: Enigma Variations
この演奏会は今シーズンのチケット発売開始後あっという間に売り切れになっていて、さすがヴェンゲーロフは人気者、と思っていたのですが、実はThe Queen's Medal for Musicのガラコンサートということで、女王陛下も臨席されるスペシャルイベントだったんですね。当初はサー・コリン・デイヴィスが指揮の予定でしたが、例によってドクターストップでキャンセル。今シーズン目玉の一つであったはずの一連の「デイヴィス卿85歳記念コンサート」は、結局ここまで一つも振れてません。このままカムバックしなかったら、シャレにならんよ。
物々しいセキュリティチェックを覚悟していたら、いつも通りコート着たまま、リュック担いだまますんなりと会場に入れたのでちょっと拍子抜け。しかし、女王は全員が着席してからの入場のため、普段よりも早く席に着かされました。最初はLSO on Trackという教育プログラムの若者管楽器奏者も加わっての短いファンファーレがあり、続く国歌斉唱の後、今回の委嘱新作であるマックスウェル・デイヴィスの「女王陛下歓迎のファンファーレ」が演奏されました。しかしこのファンファーレ、しゃきんとしたところが一切ない屈折したヘンテコな曲で、このシニカルさはイギリス音楽としては意味があるのかもしれませんが、女王陛下はこの曲で歓迎されて果たして嬉しいのか、とちょっと気になりました。なお、ここまでの指揮はティモシー・レッドモンドです。
次のチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲は、正直苦手な曲。チャイコフスキーは好きですが、この曲はやっつけ仕事に見えてならず、皆が崇めるほど、そんなに名曲かなあと常々疑問に思っています。それはともかく、第1楽章の特に前半は、ヴェンゲーロフの隙のない完璧さに感服しました。じっくり分析して積み上げたという感じはなく、天才が腹八分目で弾いているような、衒いのないナチュラルな上手さ。ところがそのうち雲行きが怪しくなって、「ん」と思ってしまう箇所がちらほら耳に残ってきます。カデンツァも「ボロボロ」とは言わないまでも「ボロ」くらいは言ってしまえる不調ぶり。もちろん、彼にしては、という但し書きはつきますが。どうしちゃったんだろう、ソリストとして復帰してまだ日が浅いので、リハビリ途中なのかもしれません。それにしてもこの人は終始直立不動、第2楽章でかかとが少し浮いた以外は、足なんかほとんど動きません。また肩をいわさなければ良いのですが。終楽章は曲芸のようなスピードで激しく駆け抜け、ヴァイオリン・ヴィルトゥオーソの面目躍如で圧巻した。オケは女王臨席だとさすがに集中力極大で、切れのあるリズムにふくよかな音色、完璧なパートバランスと三拍子勢ぞろい。サー・コリンの代役のティッチアーティも伸び伸びとオケを引っ張り、良い仕事でした。
Robin Ticciati / London Symphony Orchestra
Timothy Redmond (conductor-1)
Maxim Vengerov (violin-2)
1. Maxwell Davies: Fanfare - Her Majesty's Welcome (LSO commission)
2. Tchaikovsky: Violin Concerto
3. Elgar: Enigma Variations
この演奏会は今シーズンのチケット発売開始後あっという間に売り切れになっていて、さすがヴェンゲーロフは人気者、と思っていたのですが、実はThe Queen's Medal for Musicのガラコンサートということで、女王陛下も臨席されるスペシャルイベントだったんですね。当初はサー・コリン・デイヴィスが指揮の予定でしたが、例によってドクターストップでキャンセル。今シーズン目玉の一つであったはずの一連の「デイヴィス卿85歳記念コンサート」は、結局ここまで一つも振れてません。このままカムバックしなかったら、シャレにならんよ。
物々しいセキュリティチェックを覚悟していたら、いつも通りコート着たまま、リュック担いだまますんなりと会場に入れたのでちょっと拍子抜け。しかし、女王は全員が着席してからの入場のため、普段よりも早く席に着かされました。最初はLSO on Trackという教育プログラムの若者管楽器奏者も加わっての短いファンファーレがあり、続く国歌斉唱の後、今回の委嘱新作であるマックスウェル・デイヴィスの「女王陛下歓迎のファンファーレ」が演奏されました。しかしこのファンファーレ、しゃきんとしたところが一切ない屈折したヘンテコな曲で、このシニカルさはイギリス音楽としては意味があるのかもしれませんが、女王陛下はこの曲で歓迎されて果たして嬉しいのか、とちょっと気になりました。なお、ここまでの指揮はティモシー・レッドモンドです。
次のチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲は、正直苦手な曲。チャイコフスキーは好きですが、この曲はやっつけ仕事に見えてならず、皆が崇めるほど、そんなに名曲かなあと常々疑問に思っています。それはともかく、第1楽章の特に前半は、ヴェンゲーロフの隙のない完璧さに感服しました。じっくり分析して積み上げたという感じはなく、天才が腹八分目で弾いているような、衒いのないナチュラルな上手さ。ところがそのうち雲行きが怪しくなって、「ん」と思ってしまう箇所がちらほら耳に残ってきます。カデンツァも「ボロボロ」とは言わないまでも「ボロ」くらいは言ってしまえる不調ぶり。もちろん、彼にしては、という但し書きはつきますが。どうしちゃったんだろう、ソリストとして復帰してまだ日が浅いので、リハビリ途中なのかもしれません。それにしてもこの人は終始直立不動、第2楽章でかかとが少し浮いた以外は、足なんかほとんど動きません。また肩をいわさなければ良いのですが。終楽章は曲芸のようなスピードで激しく駆け抜け、ヴァイオリン・ヴィルトゥオーソの面目躍如で圧巻した。オケは女王臨席だとさすがに集中力極大で、切れのあるリズムにふくよかな音色、完璧なパートバランスと三拍子勢ぞろい。サー・コリンの代役のティッチアーティも伸び伸びとオケを引っ張り、良い仕事でした。
休憩後、実はこのイベントの予備知識を何も仕入れていない私は、今年の受賞者の発表も当日行われることをその場になってはじめて知りました。女王陛下も舞台に出てこられて、ホストのマックスウェル・デイヴィスより今年の受賞者である英国ナショナルユース管弦楽団(NYO)の名が読み上げられました。個人でなく団体に賞が与えられるのは初とのことです。女王臨席の演奏会で御大デイヴィス卿の代役に超若手のティッチアーティはちょっと軽すぎるんじゃないかと思っていたのですが、なるほど、NYOの受賞が決まっていたのでその出身者を持ってきたのね、というのはうがった見方でしょうか。ともあれNYOは来年早々にバービカンで演奏会がありますので、よい凱旋公演となることでしょう。それにしても今日は前から二列目の席だったので女王陛下とは5mもない至近距離。特に女王ファンと言うわけではありませんが、こんなに近づけることも今後二度とないと思うので、貴重な経験でした。
NYOを代表して5人の若者が登壇、女王と握手していました。
最後のエニグマ変奏曲がこれまた素晴らしい演奏で、気合の入ったときのLSOの音が何と豊かで艶やかなことよ。節度を守りつつも仄かに感傷を漂わせる絶妙の「ニムロッド」で、まさに時が止まりました。指揮者も若いのに余裕たっぷりの指揮ぶりで、とんでもない大器かもしれません。
全部終わったらもう10時。混雑する前に会場を出ようとしたら階段が閉鎖されていて、仕方なしに駐車場のほうから外に出ると、ちょうど裏口から女王がロイヤルカーで帰宅するところでした。周囲は通りがかりの車も全て足止めされていて、やっぱりやんごとなきお人が動くのはいろいろたいへんやなあと。
シャッターチャンスを逃し、女王の顔が見えない…。
エリーナ・ガランチャ@バービカン ― 2012/10/02 23:59
2012.10.02 Barbican Hall (London)
Elina Garanča (Ms)
Karel Mark Chichon / London Symphony Orchestra
Gordon Nikolitch (Vn-3)
1. Glinka: Overture to "Ruslan and Ludmila"
2. Tchaikovsky: "Yes, the time has come" from "The Maid of Orleans"
3. Massenet: Meditation from "Thaïs"
4. Saint-Saëns: "Mon coeur s’ouvre à ta voix" from "Samson et Dalila"
5. Saint-Saëns: Bacchanale from "Samson et Dalila"
6. Gounod: "Plus grand, dans son obscurité" from "La Reine de Saba"
7. Pascal Marquina Norro: España Cañí
8. Santiago Lope Gonzalo: Gerona
9. Manuel Penella: Pasodoble from "El gato montés"
10. Bizet: Extracts from "Carmen"
1) Prélude (Act I)
2) Habanera (Act I)
3) Entr’acte (Act III)
4) Séguedille (Act I)
5) Entr’acte (Act IV)
6) En vain, pour éviter (Act III)
7) Entr’acte (Act II)
8) Chanson bohème (Act II)
このように歌手を前面に立てた「オペラアリアの夕べ」みたいなのは、器楽志向の私は最も避けてきた部類の演奏会ですが、一度は見たいと思っていたエリーナ・ガランチャを今シーズンもオペラ座で見ることはできなさそうだというのが判明してから、ちょうど頃合よく目に付いたこのチケットを思わず買ってしまいました。何でもこのコンサートはドイツ・グラモフォンから先月発売されたばかりの新譜「Romantique」のプロモーション・ツアーの一環だそうです。それにしてもバックがLSOとは豪勢な話。指揮者は聞いたことがない名前でしたが、ガランチャのダンナさんなんですね。
1曲目の「ルスランとリュドミラ」序曲が終わり、入場してきたガランチャは、今まで見たどのプロモーション写真とも違う(笑)、シックなグレーのドレスに身を包んだ、がっしりとした体格の飾りっ気ない中年女性でした。もっと細身で色気たっぷりのお姉ちゃんを想像していた私は思いっきり肩すかし。30代半ばにしてはちょっと老け顔だし、身体の線も、ちょっと…。
いや、だってね、
Elina Garanča (Ms)
Karel Mark Chichon / London Symphony Orchestra
Gordon Nikolitch (Vn-3)
1. Glinka: Overture to "Ruslan and Ludmila"
2. Tchaikovsky: "Yes, the time has come" from "The Maid of Orleans"
3. Massenet: Meditation from "Thaïs"
4. Saint-Saëns: "Mon coeur s’ouvre à ta voix" from "Samson et Dalila"
5. Saint-Saëns: Bacchanale from "Samson et Dalila"
6. Gounod: "Plus grand, dans son obscurité" from "La Reine de Saba"
7. Pascal Marquina Norro: España Cañí
8. Santiago Lope Gonzalo: Gerona
9. Manuel Penella: Pasodoble from "El gato montés"
10. Bizet: Extracts from "Carmen"
1) Prélude (Act I)
2) Habanera (Act I)
3) Entr’acte (Act III)
4) Séguedille (Act I)
5) Entr’acte (Act IV)
6) En vain, pour éviter (Act III)
7) Entr’acte (Act II)
8) Chanson bohème (Act II)
このように歌手を前面に立てた「オペラアリアの夕べ」みたいなのは、器楽志向の私は最も避けてきた部類の演奏会ですが、一度は見たいと思っていたエリーナ・ガランチャを今シーズンもオペラ座で見ることはできなさそうだというのが判明してから、ちょうど頃合よく目に付いたこのチケットを思わず買ってしまいました。何でもこのコンサートはドイツ・グラモフォンから先月発売されたばかりの新譜「Romantique」のプロモーション・ツアーの一環だそうです。それにしてもバックがLSOとは豪勢な話。指揮者は聞いたことがない名前でしたが、ガランチャのダンナさんなんですね。
1曲目の「ルスランとリュドミラ」序曲が終わり、入場してきたガランチャは、今まで見たどのプロモーション写真とも違う(笑)、シックなグレーのドレスに身を包んだ、がっしりとした体格の飾りっ気ない中年女性でした。もっと細身で色気たっぷりのお姉ちゃんを想像していた私は思いっきり肩すかし。30代半ばにしてはちょっと老け顔だし、身体の線も、ちょっと…。
いや、だってね、




こんな美女が出てくるのかっ、とワクワクしていたら、この中の誰とも違う人が出てきたので…。(失礼)
オケの間奏を挟みながら進行するプログラムの前半は、チャイコフスキー「オルレアンの少女」、サン=サーンス「サムソンとデリラ」、グノー「シバの女王」から各々メジャーなアリアを取り揃えます。前半はお腹で手を組み、品格高い歌唱を心がけていました。LSOがよく鳴るのでオケがうるさ過ぎのところもありましたが、それにも負けずによく通る美声でした。メゾソプラノの太さはそのままに、ソプラノのように突き抜けたロングトーンの伸びは、天性のものがありますね。私はこのへんのオペラアリアはさっぱりわからないのですが、声の特質をよく活かした、じっくり聴かせる選曲になっていました。
後半はスパニッシュ特集。黒いドレスと深紅の口紅にお召し替え、前半よりもくだけた感じで小芝居の入ったシアトリカルな歌唱にイメチェン。「カルメン」はさすがのオハコで、自信たっぷり、余裕たっぷりのコロラトゥーラ・メゾ。技巧に長けていてやけに健全なカルメンという印象でした。もっと場末でヘタウマのくずれた感じもあったほうが、全くのアウトローである本来のカルメンのキャラクターには合う気もしますが、それはそれとしてもガランチャは是非ともオペラ座で見たかった。3年前にアラーニャとのコンビでROHの「カルメン」に出演したとき、我が家はまだROHデビュー前だったので見てないのです…。
ダンナさんのチチョンは、オペラ指揮者にはありがちな、カリスマはないけど仕事きっちりのタイプで、結構若いのに手慣れた棒さばきでLSOを鳴らし、安定感がありました。愛妻のためとは言え、この雑多なプログラムを全部暗譜でやってたのは立派。ガランチャも後半は終始リラックスした表情で上機嫌、アンコールではスペイン系をさらに3曲歌ってくれました。
LSO/ドナテッラ・フリック欧州指揮者コンクール ― 2012/09/30 23:59
2012.09.30 Barbican Hall (London)
Donatella Flick LSO Conducting Competition 2012: Final
Finalists:
A. Ben Gernon British, Age 23
B. Stamatia Karampini Greek, Age 34
C. Alexandre Bloch French, Age 27
London Symphony Orchestra
1. Weber: "Der Freischütz" Overture
Performed three times, conducted in turn by each finalist
2. Debussy: La mer
2-1) De l'aube à midi sur la mer (From dawn to noon on the sea)
Stamatia Karampini (Conductor)
2-2) Jeux de vagues (The play of the waves)
Alexandre Bloch (Conductor)
2-3) Dialogue du vent et de la mer (Dialogue of the wind and the sea)
Ben Gernon (Conductor)
3. Prokofiev: Romeo and Juliet – Suites Nos 1 & 2
3-1) Suite 1, No. 4: Minuet
3-2) Suite 2, No. 6: Dance of the Antilles Girls
3-3) Suite 1, No. 7: Death of Tybalt
Alexandre Bloch (Conductor)
3-4) Suite 1, No. 2: Scene
3-5) Suite 2, No. 2: Juliet the Young Girl
3-6) Suite 1, No. 5: Masks
Ben Gernon (Conductor)
3-7) Suite 2, No. 4: Dance
3-8) Suite 2, No. 7: Romeo at Juliet's Grave
3-9) Suite 2, No. 1: Montagues and Capulets
Stamatia Karampini (Conductor)
27日のデイヴィス85歳記念コンサート第1弾は肝心要のデイヴィス翁と、さらには内田光子まで体調不良でキャンセルになってしまったため当然の如くチケットをリターン(目当てはルプーだったので彼さえ出てくれれば良かったんですがねえ、何で一緒にキャンセルするんだか)、今日が今シーズンのLSO開幕になります。
我ながら物好きとは思いつつも、この日は通常の演奏会ではなくDonatella Flick指揮者コンクールの最終選考会。1990年以来隔年で開催されており、パトロンはチャールズ皇太子です。応募資格はEUに国籍を持つ35歳以下の若者で、優勝者は賞金15000ポンドとLSOのアシスタントコンダクターのポジションを得ます(1年間)。不勉強ながら私はこのコンクールを知らなかったのですが、過去の優勝者の顔ぶれを見ても正直知らない人がほとんどです。
審査委員長はLSOチェアマンのマッケンジー。今年の審査員はコリン・デイヴィス(病欠しましたが)、パッパーノ大将、ニコラス・ズナイダー、イモゲン・クーパーに、LSOの首席奏者2名、聖チェチーリア音楽院の芸術スタッフが加わっています。審査員の顔ぶれは他の指揮者コンクールと比べても豪華なほうだと思います。まず、ビデオ選考で選抜された20名がロンドンで3日に渡り行われる最終選考会に進みますが、最初の2日間はギルドホール音楽演劇学校のオケを相手にリハーサルおよび指揮する様子を審査されます。初日はモーツァルトのプラハ交響曲、シューベルトの未完成などが課題に出され、そこで10名がふるい落とされます。2日目は協奏曲(ヴァイオリン)、オペラのレチタティーヴォ、コンテンポラリーの新作といったより幅の広い対応が求められ、勝ち抜いた3名がバービカンでLSOを振る最終選考会に臨みます。ファイナリストは23歳イギリス人のベン・ジャーノン、34歳ギリシャ人の紅一点スタマティア・カランピニ、27歳フランス人のアレクサンドル・ブロッホ。若いベン君はともかく、他の二人はすでに国際プロ指揮者としてのキャリアをそれなりに積んでいるようです。
1曲目は「魔弾の射手」序曲を順番に3回演奏するという趣向。そう言えばこの曲は昔部活でやったっけなあ、と懐かしく思い出しました。指揮者コンクールというものを見るのは実は初めてだったのですが、これはなかなかジャッジの難しい競技会です。ファイナリストに残るくらいだからバトンテクは皆さんもちろん一様に申し分なく、解釈においても著しく個性的な人はいません。指揮者が交代してさっきとは音が変わったなという引っかかりは感じても、それが指揮者の所業なのか、オケの演奏のムラなのか、素人には見通す力が足りません。多分プロはプロの見方があるんでしょうけど。
トップバッターのベン君はテンポにメリハリを付けた熱い演奏でしたが、アインザッツの乱れがあって多少荒いという印象。「肝っ玉母さん」という雰囲気のスタマちゃんは(実際に母親なのか、既婚かどうかも知りませんが)、落ち着いた進行に柔らかい肌触りの、経験を感じさせる中庸の演奏。最後のアレックス君は細身の身体に肘の高い腕の振りがダイナミックで、実際にはベン君とさほど身長は変わらないのにかなり長身に見えます。3番手という有利もあったのでしょうが、この人が一番自然な音をオケから引出し、ドライブも上手く、完璧なプロポーションで曲の起伏を作っていました。面白かったのは、3人が3人とも、序奏の後やコーダ手前ではテンポ前のめりで突っ込んでいたことで、これなどは1番手のベン君のドライブをオケのほうが後の人にも引きずってしまった結果ではなかろうかと。何にせよ、同じ曲を連続して演奏するときは気持ちの上でも最初と最後が得、真ん中はちょっと損ですね。
2曲目のドビュッシー「海」は、3つの楽章を分け合って一人ずつ指揮します。今度は逆に、曲想的には第2曲が一番盛り上げやすくて得だったんじゃないかと個人的に思いましたが、まあそのへんのくじ運の差異はもちろん考慮しつつ審査されるんでしょう。しかし、フェアな感想として2番手のアレックス君が最も多彩な色彩感を持っていたのも事実で(というより他の二人はカラフルとは言い難い演奏だった)、フランス人の彼にとって「ご当地もの」だったのも良かったでしょう。最後の「ロメオとジュリエット」でもくじ運の当たり外れがありそうでした。最初と最後の要所を2曲も含む3番手スタマちゃん、最も劇的なクライマックスの「ティボルトの死」をゲットした1番手アレックス君と比べて、2番手のベン君は音楽だけで聴かせるにはちときつい場面ばかり、割を食いました。
全員の演奏終了後、審査員が結論を出すまでの間に、初日から3日目のLSOとのリハに至るまでの様子をインタビューを交えて編集した20分くらいのビデオが上映され、その後さらに10分ほど待たされて、ようやく結果発表と表彰の式典が始まりました。私の評価では、全ての曲において演奏にしなやかさとしたたかさが最もあったのは鉄板でアレックス君。この中から一人選べと言われたら彼しかないと思ったら、審査結果もやっぱりその通りでした。モジャモジャ頭がどこかドゥダメルを髣髴とさせる明るく朴訥な雰囲気は、使いようによっては面白いキャラかも。今後ロンドンで是非活躍してもらいたいものです。ベン君はいろんな意味でまだ若かった。スタマちゃんは後で調べると、昨年の有名なブザンソン国際指揮者コンクールでも3人のファイナリストに残った実力者でしたが、垣内悠希さんに優勝をさらわれました。今回またしても後一歩のところで優勝を逃し、年齢的に言ってもさぞ悔しかったと思いますが、すでにプロ指揮者としてのキャリアは重ねているわけだから、これをバネに一皮向けてくれたらと思います。
Donatella Flick LSO Conducting Competition 2012: Final
Finalists:
A. Ben Gernon British, Age 23
B. Stamatia Karampini Greek, Age 34
C. Alexandre Bloch French, Age 27
London Symphony Orchestra
1. Weber: "Der Freischütz" Overture
Performed three times, conducted in turn by each finalist
2. Debussy: La mer
2-1) De l'aube à midi sur la mer (From dawn to noon on the sea)
Stamatia Karampini (Conductor)
2-2) Jeux de vagues (The play of the waves)
Alexandre Bloch (Conductor)
2-3) Dialogue du vent et de la mer (Dialogue of the wind and the sea)
Ben Gernon (Conductor)
3. Prokofiev: Romeo and Juliet – Suites Nos 1 & 2
3-1) Suite 1, No. 4: Minuet
3-2) Suite 2, No. 6: Dance of the Antilles Girls
3-3) Suite 1, No. 7: Death of Tybalt
Alexandre Bloch (Conductor)
3-4) Suite 1, No. 2: Scene
3-5) Suite 2, No. 2: Juliet the Young Girl
3-6) Suite 1, No. 5: Masks
Ben Gernon (Conductor)
3-7) Suite 2, No. 4: Dance
3-8) Suite 2, No. 7: Romeo at Juliet's Grave
3-9) Suite 2, No. 1: Montagues and Capulets
Stamatia Karampini (Conductor)
27日のデイヴィス85歳記念コンサート第1弾は肝心要のデイヴィス翁と、さらには内田光子まで体調不良でキャンセルになってしまったため当然の如くチケットをリターン(目当てはルプーだったので彼さえ出てくれれば良かったんですがねえ、何で一緒にキャンセルするんだか)、今日が今シーズンのLSO開幕になります。
我ながら物好きとは思いつつも、この日は通常の演奏会ではなくDonatella Flick指揮者コンクールの最終選考会。1990年以来隔年で開催されており、パトロンはチャールズ皇太子です。応募資格はEUに国籍を持つ35歳以下の若者で、優勝者は賞金15000ポンドとLSOのアシスタントコンダクターのポジションを得ます(1年間)。不勉強ながら私はこのコンクールを知らなかったのですが、過去の優勝者の顔ぶれを見ても正直知らない人がほとんどです。
審査委員長はLSOチェアマンのマッケンジー。今年の審査員はコリン・デイヴィス(病欠しましたが)、パッパーノ大将、ニコラス・ズナイダー、イモゲン・クーパーに、LSOの首席奏者2名、聖チェチーリア音楽院の芸術スタッフが加わっています。審査員の顔ぶれは他の指揮者コンクールと比べても豪華なほうだと思います。まず、ビデオ選考で選抜された20名がロンドンで3日に渡り行われる最終選考会に進みますが、最初の2日間はギルドホール音楽演劇学校のオケを相手にリハーサルおよび指揮する様子を審査されます。初日はモーツァルトのプラハ交響曲、シューベルトの未完成などが課題に出され、そこで10名がふるい落とされます。2日目は協奏曲(ヴァイオリン)、オペラのレチタティーヴォ、コンテンポラリーの新作といったより幅の広い対応が求められ、勝ち抜いた3名がバービカンでLSOを振る最終選考会に臨みます。ファイナリストは23歳イギリス人のベン・ジャーノン、34歳ギリシャ人の紅一点スタマティア・カランピニ、27歳フランス人のアレクサンドル・ブロッホ。若いベン君はともかく、他の二人はすでに国際プロ指揮者としてのキャリアをそれなりに積んでいるようです。
1曲目は「魔弾の射手」序曲を順番に3回演奏するという趣向。そう言えばこの曲は昔部活でやったっけなあ、と懐かしく思い出しました。指揮者コンクールというものを見るのは実は初めてだったのですが、これはなかなかジャッジの難しい競技会です。ファイナリストに残るくらいだからバトンテクは皆さんもちろん一様に申し分なく、解釈においても著しく個性的な人はいません。指揮者が交代してさっきとは音が変わったなという引っかかりは感じても、それが指揮者の所業なのか、オケの演奏のムラなのか、素人には見通す力が足りません。多分プロはプロの見方があるんでしょうけど。
トップバッターのベン君はテンポにメリハリを付けた熱い演奏でしたが、アインザッツの乱れがあって多少荒いという印象。「肝っ玉母さん」という雰囲気のスタマちゃんは(実際に母親なのか、既婚かどうかも知りませんが)、落ち着いた進行に柔らかい肌触りの、経験を感じさせる中庸の演奏。最後のアレックス君は細身の身体に肘の高い腕の振りがダイナミックで、実際にはベン君とさほど身長は変わらないのにかなり長身に見えます。3番手という有利もあったのでしょうが、この人が一番自然な音をオケから引出し、ドライブも上手く、完璧なプロポーションで曲の起伏を作っていました。面白かったのは、3人が3人とも、序奏の後やコーダ手前ではテンポ前のめりで突っ込んでいたことで、これなどは1番手のベン君のドライブをオケのほうが後の人にも引きずってしまった結果ではなかろうかと。何にせよ、同じ曲を連続して演奏するときは気持ちの上でも最初と最後が得、真ん中はちょっと損ですね。
2曲目のドビュッシー「海」は、3つの楽章を分け合って一人ずつ指揮します。今度は逆に、曲想的には第2曲が一番盛り上げやすくて得だったんじゃないかと個人的に思いましたが、まあそのへんのくじ運の差異はもちろん考慮しつつ審査されるんでしょう。しかし、フェアな感想として2番手のアレックス君が最も多彩な色彩感を持っていたのも事実で(というより他の二人はカラフルとは言い難い演奏だった)、フランス人の彼にとって「ご当地もの」だったのも良かったでしょう。最後の「ロメオとジュリエット」でもくじ運の当たり外れがありそうでした。最初と最後の要所を2曲も含む3番手スタマちゃん、最も劇的なクライマックスの「ティボルトの死」をゲットした1番手アレックス君と比べて、2番手のベン君は音楽だけで聴かせるにはちときつい場面ばかり、割を食いました。
全員の演奏終了後、審査員が結論を出すまでの間に、初日から3日目のLSOとのリハに至るまでの様子をインタビューを交えて編集した20分くらいのビデオが上映され、その後さらに10分ほど待たされて、ようやく結果発表と表彰の式典が始まりました。私の評価では、全ての曲において演奏にしなやかさとしたたかさが最もあったのは鉄板でアレックス君。この中から一人選べと言われたら彼しかないと思ったら、審査結果もやっぱりその通りでした。モジャモジャ頭がどこかドゥダメルを髣髴とさせる明るく朴訥な雰囲気は、使いようによっては面白いキャラかも。今後ロンドンで是非活躍してもらいたいものです。ベン君はいろんな意味でまだ若かった。スタマちゃんは後で調べると、昨年の有名なブザンソン国際指揮者コンクールでも3人のファイナリストに残った実力者でしたが、垣内悠希さんに優勝をさらわれました。今回またしても後一歩のところで優勝を逃し、年齢的に言ってもさぞ悔しかったと思いますが、すでにプロ指揮者としてのキャリアは重ねているわけだから、これをバネに一皮向けてくれたらと思います。
左からアレックス君、スタマちゃん、ベン君。
優勝者をハグで祝福するベン君。
左が創立者のドナテッラ・フリックさん。
LSO/ゲルギエフ/フレミング(s):シェヘラザードとペトルーシュカ ― 2012/07/15 23:59
2012.07.15 Barbican Hall (London)
Valery Gergiev / London Symphony Orchestra
Renée Fleming (S-2,3)
1. Debussy: La mer
2. Henri Dutilleux: Le temps l’horloge (UK premiere)
3. Ravel: Shéhérazade
4. Stravinsky: Petrushka (1911 ver.)
LSOのシーズンフィナーレは「フレミング効果」で早々にソールドアウトになってしまったため、私もずいぶん後になってからリターン狙いで、普段なら買わない高い席を選択の余地もなくゲットしました。
1曲目はドビュッシーの交響詩「海」。ゲルギエフはその外見のむさ苦しさと相反して、意外とフランスものを得意としていますね。繋ぎ目なしで一気に流した演奏は繊細の極致で、オケの集中力も素晴らしかったです。トランペットもホルンも完璧で惚れ惚れしました。オケが良いのは当然として、ゲルギーの細部を彫り込む解釈とコントロールも冴えていて、上手く言えないのですが、極上の鮮魚を切って並べただけでなく、一仕事も二仕事も入っている究極の寿司、という感じですか。
続いて待望のフレミング登場。オペラ、演奏通じて実は初めて見ます。デュティユーの歌曲「時と時計」はフレミングのために2007年に作曲され、小澤征爾指揮サイトウキネンオケとの共演で松本にて初演されました。UKでは今日が初演。二管編成にハプシコードやアコーディオンも加わる幻想的な曲で、つかみどころのない不思議なオーラを放っています。デュティユー(ってまだ現役なんですねー驚き)の曲はほとんど聴いていませんが、フレンチテイストのようでいて、仏教にも通じる「無の境地」を感じます。フレミングは表現力に卓越した歌手に思えましたが、この耳に新しい曲だけではまだ何とも。
Valery Gergiev / London Symphony Orchestra
Renée Fleming (S-2,3)
1. Debussy: La mer
2. Henri Dutilleux: Le temps l’horloge (UK premiere)
3. Ravel: Shéhérazade
4. Stravinsky: Petrushka (1911 ver.)
LSOのシーズンフィナーレは「フレミング効果」で早々にソールドアウトになってしまったため、私もずいぶん後になってからリターン狙いで、普段なら買わない高い席を選択の余地もなくゲットしました。
1曲目はドビュッシーの交響詩「海」。ゲルギエフはその外見のむさ苦しさと相反して、意外とフランスものを得意としていますね。繋ぎ目なしで一気に流した演奏は繊細の極致で、オケの集中力も素晴らしかったです。トランペットもホルンも完璧で惚れ惚れしました。オケが良いのは当然として、ゲルギーの細部を彫り込む解釈とコントロールも冴えていて、上手く言えないのですが、極上の鮮魚を切って並べただけでなく、一仕事も二仕事も入っている究極の寿司、という感じですか。
続いて待望のフレミング登場。オペラ、演奏通じて実は初めて見ます。デュティユーの歌曲「時と時計」はフレミングのために2007年に作曲され、小澤征爾指揮サイトウキネンオケとの共演で松本にて初演されました。UKでは今日が初演。二管編成にハプシコードやアコーディオンも加わる幻想的な曲で、つかみどころのない不思議なオーラを放っています。デュティユー(ってまだ現役なんですねー驚き)の曲はほとんど聴いていませんが、フレンチテイストのようでいて、仏教にも通じる「無の境地」を感じます。フレミングは表現力に卓越した歌手に思えましたが、この耳に新しい曲だけではまだ何とも。
休憩後、再び登場のフレミングで今度はラヴェルの歌曲集「シェヘラザード」。この曲は音源を持っておらず、2004年のブダペスト以来8年ぶりに聴きま す。意味深な歌詞にラヴェルの熟達した管弦楽法が絡み合ったオシャレな佳作です。フレミングの歌はそりゃー上手いし、繊細だし、情緒もありましたが、声自 体は普通で、私の好みとはちょっと違うかなと。オペラはもう大劇場でスポット的にしか出てないようですが、もうちょっと若いころは声に厚みがあってさぞ舞 台映えするソプラノだったんだろうと思います。チケット争奪の激しさを考えると、どうしてもまた聴いてみたい歌手とは思えなかったです、すいません。
最後の「ペトルーシュカ」は1911年版。今シーズンのストラヴィンスキーシリーズの最終でもあります。オケ奏者的にはイラっとする曲ばかり続いたせいで最後に集中力が切れたか、あるいは単なるリハ不足か、だいぶアラが目立ちました。トランペットのコッブは珍しく音を外すし、もっと珍しいのはティンパニのトーマスも1小節飛び出してしまう大ポカをやらかし、何だか落ち着きがありませんでした。本来は主役で活躍するはずのピアノも何だか地味で引っ込んでいて、ちぐはぐな「ペトルーシュカ」でした。ゲルギーのアイデアは豊富でいろいろとやらかそうとするけれど、まだオケと一体化していないんじゃないかという印象です。ペトルーシュカはできたら舞台付きで見たいものです。人形劇では見ましたが、一度バレエで見てみたいですなー。
LSO/ハイティンク/ピレシュ(p):巨匠・ザ・グレート ― 2012/06/10 23:59
2012.06.10 Barbican Hall (London)
Bernard Haitink / London Symphony Orchestra
Maria João Pires (P-2)
1. Purcell: Chacony in G minor
2. Mozart: Piano Concerto No. 20
3. Schubert: Symphony No. 9 (‘The Great’)
モーツァルトとシューベルトなんて私としては非常に珍しい選択ですが、リターンバウチャーを使いたかったのと、久々に「グレート」を聴いてみたくなったので。
去年もシーズン終盤の6月にバービカンでハイティンク、ピレシュの共演を聴きましたが、季節の風物詩なんですかね。ピレシュは磐石なテクニックに、くっきりした音の粒のたいへん品の良いピアノ。昨年の備忘録を読み直してみると、ほとんど同じ感想を書いてました。小柄でパワーはなさそうなのに、ハイティンクのちょっと重めのオケに埋もれず、サークル席でも非常にクリアに聴こえてきました。オケは少し低めの重心で堅牢な土台を作り、その上で安心して踊っているピレシュのピアノは、澱み、迷い、引っかかりが一切なく、実に自然に心に響いてきて、今更ながら「ええ曲やなー」と聴き入ってしまいました。モーツァルトのピアノ協奏曲を聴いていて沈没しなかったのはほとんど初めてかも。なお、ティンパニはクレジットされてなかったけどプリンシパルのナイジェル・トーマスが叩いてました。
メインの「ザ・グレート」はかつて部活のオケでやったことがある曲なので(自分の出番はなかったですが)さんざ聴き込みました。生で聴くのはえらいこと久しぶりで、新婚の旅行でザンデルリンク/フィルハーモニア管の演奏をロイヤル・フェスティヴァル・ホールで聴いて以来。それ以降積極的に聴きたいとも思わなかったし縁もなかったのですが、長い年月を経て次に巡ってきた機会が、再びロンドンというのは感慨深いです。古き良き巨匠時代の生き残りハイティンク御大だから、コッテリ高カロリーでミシミシと踏みしめるように行くのかと思っていたら、予想に反して快速テンポでテキパキとぶっ飛ばしました。序奏と第1主題でテンポの差があまりなかったです。先のモーツァルトよりもまた少し重心を下げ、先日のブルックナーと比べても旋律の歌わせ方などは意外と雄弁で、細かくいじり込まなくても本来の音楽の力だけでこれだけ語ってしまうところなど、ハイティンクは曲もオケ(LSO)も十分に知り尽くしています。対照的に終楽章はアレグロ・ヴィヴァーチェとしては多少遅めくらいのテンポで、セカセカしないように地に足がついた歩みっぷり。巨匠の懐の深さを垣間見ました。こちらのティンパニはクレジットされていたAntoine Bedewi(アントワン・ベドウィと読むの?)。LSOではパーカッションを叩いているほうが多い人ですが、まれにセカンドティンパニにも入っています。硬質のバチで乾いた音を叩き出すトーマス流で、この人も普通に上手かったです。ハイティンク御大はさすがの人気で、いつものように会場総立ちの大拍手。いつものごとくアンコールは無しでした。
Bernard Haitink / London Symphony Orchestra
Maria João Pires (P-2)
1. Purcell: Chacony in G minor
2. Mozart: Piano Concerto No. 20
3. Schubert: Symphony No. 9 (‘The Great’)
モーツァルトとシューベルトなんて私としては非常に珍しい選択ですが、リターンバウチャーを使いたかったのと、久々に「グレート」を聴いてみたくなったので。
去年もシーズン終盤の6月にバービカンでハイティンク、ピレシュの共演を聴きましたが、季節の風物詩なんですかね。ピレシュは磐石なテクニックに、くっきりした音の粒のたいへん品の良いピアノ。昨年の備忘録を読み直してみると、ほとんど同じ感想を書いてました。小柄でパワーはなさそうなのに、ハイティンクのちょっと重めのオケに埋もれず、サークル席でも非常にクリアに聴こえてきました。オケは少し低めの重心で堅牢な土台を作り、その上で安心して踊っているピレシュのピアノは、澱み、迷い、引っかかりが一切なく、実に自然に心に響いてきて、今更ながら「ええ曲やなー」と聴き入ってしまいました。モーツァルトのピアノ協奏曲を聴いていて沈没しなかったのはほとんど初めてかも。なお、ティンパニはクレジットされてなかったけどプリンシパルのナイジェル・トーマスが叩いてました。
メインの「ザ・グレート」はかつて部活のオケでやったことがある曲なので(自分の出番はなかったですが)さんざ聴き込みました。生で聴くのはえらいこと久しぶりで、新婚の旅行でザンデルリンク/フィルハーモニア管の演奏をロイヤル・フェスティヴァル・ホールで聴いて以来。それ以降積極的に聴きたいとも思わなかったし縁もなかったのですが、長い年月を経て次に巡ってきた機会が、再びロンドンというのは感慨深いです。古き良き巨匠時代の生き残りハイティンク御大だから、コッテリ高カロリーでミシミシと踏みしめるように行くのかと思っていたら、予想に反して快速テンポでテキパキとぶっ飛ばしました。序奏と第1主題でテンポの差があまりなかったです。先のモーツァルトよりもまた少し重心を下げ、先日のブルックナーと比べても旋律の歌わせ方などは意外と雄弁で、細かくいじり込まなくても本来の音楽の力だけでこれだけ語ってしまうところなど、ハイティンクは曲もオケ(LSO)も十分に知り尽くしています。対照的に終楽章はアレグロ・ヴィヴァーチェとしては多少遅めくらいのテンポで、セカセカしないように地に足がついた歩みっぷり。巨匠の懐の深さを垣間見ました。こちらのティンパニはクレジットされていたAntoine Bedewi(アントワン・ベドウィと読むの?)。LSOではパーカッションを叩いているほうが多い人ですが、まれにセカンドティンパニにも入っています。硬質のバチで乾いた音を叩き出すトーマス流で、この人も普通に上手かったです。ハイティンク御大はさすがの人気で、いつものように会場総立ちの大拍手。いつものごとくアンコールは無しでした。
この距離だと、ピンボケどうのこうのより、私のカメラの限界を超えてます。
おまけ。今日初めて気付いた、バービカンのパーキングの天井にあった謎のオブジェ。
LSO/MTT/ブロンフマン(p)/シャハム(vn):ベルクとマーラー ― 2012/05/31 23:59
2012.05.31 Barbican Hall (London)
Michael Tilson Thomas / London Symphony Orchestra
Yefim Bronfman (P-1), Gil Shaham (Vn-1)
1. Berg: Chamber Concerto
2. Mahler: Symphony No. 1 (‘Titan’)
日曜日に続き、MTTのマーラーミニチクルス第2弾ですが、まずはベルクの室内協奏曲から。演奏に先立ってMTTによる曲のモチーフ解説があり、その後、満を持してソリスト登場。前回はウイルス感染でキャンセルしたブロンフマンは仏頂面ながら見たところ顔色は良さそうで、対するシャハムはいつものごとく幸せそうな福顔。私、よく考えたらこの曲はおろか、ベルクの曲を実演で聴くのはほとんど初めてだったかも。新ウィーン楽派の音楽は別に嫌いではないんですが、感覚的にすっと入ってこないので、特に器楽曲はどれを聴いても区別がよくわからないのが正直なところ。この曲も正に12音、正にゲンダイオンガクの典型的、類型的な様相にしか見えなくて、さっぱりわからんかったと言うほかないです。ソリストの熱演はビジュアル的に楽しめましたし、頭痛も眠気もありませんでしたが、非常に困ったのは隣りに座った相撲取りのように巨漢のおっさん。お尻が席に収まりきらず完全にはみ出しており、幸い反対側の隣席が空いていたので一つ移動したのですが、それでも圧迫感と汗臭さは伝わってきて、なおかつ演奏中は始終「スー、ハー」と苦しそうな口呼吸をしていて、うるさいことこの上なし。背骨で自重を支えきれないのか隣りの席(私の元の席)に時々手を付き、そのたびに座席がミシミシッと悲鳴を上げて、ともかくとても演奏に集中できる環境ではありませんでした。あんたは演奏会を聴きに来る前に、医者に行ったほうがよいんではないですかい?とにかく、これではたまらんと、ストールの反対側で空いている席を物色し、休憩時間に移動しました。
Michael Tilson Thomas / London Symphony Orchestra
Yefim Bronfman (P-1), Gil Shaham (Vn-1)
1. Berg: Chamber Concerto
2. Mahler: Symphony No. 1 (‘Titan’)
日曜日に続き、MTTのマーラーミニチクルス第2弾ですが、まずはベルクの室内協奏曲から。演奏に先立ってMTTによる曲のモチーフ解説があり、その後、満を持してソリスト登場。前回はウイルス感染でキャンセルしたブロンフマンは仏頂面ながら見たところ顔色は良さそうで、対するシャハムはいつものごとく幸せそうな福顔。私、よく考えたらこの曲はおろか、ベルクの曲を実演で聴くのはほとんど初めてだったかも。新ウィーン楽派の音楽は別に嫌いではないんですが、感覚的にすっと入ってこないので、特に器楽曲はどれを聴いても区別がよくわからないのが正直なところ。この曲も正に12音、正にゲンダイオンガクの典型的、類型的な様相にしか見えなくて、さっぱりわからんかったと言うほかないです。ソリストの熱演はビジュアル的に楽しめましたし、頭痛も眠気もありませんでしたが、非常に困ったのは隣りに座った相撲取りのように巨漢のおっさん。お尻が席に収まりきらず完全にはみ出しており、幸い反対側の隣席が空いていたので一つ移動したのですが、それでも圧迫感と汗臭さは伝わってきて、なおかつ演奏中は始終「スー、ハー」と苦しそうな口呼吸をしていて、うるさいことこの上なし。背骨で自重を支えきれないのか隣りの席(私の元の席)に時々手を付き、そのたびに座席がミシミシッと悲鳴を上げて、ともかくとても演奏に集中できる環境ではありませんでした。あんたは演奏会を聴きに来る前に、医者に行ったほうがよいんではないですかい?とにかく、これではたまらんと、ストールの反対側で空いている席を物色し、休憩時間に移動しました。
メインのマーラー「巨人」は、先日の4番ほどには感心できない、ちょっと期待はずれの演奏でした。冒頭の木管下降音からして早速ばらけてますし、音が汚い。続くホルンのピッチも、これがLSOと思うくらい悪かったです。MTTは今度は指揮棒を使って、かなり大胆にテンポを動かして表情付けした音楽を導こうとしているので、主題が始まってもかえって息の合ってなさが目立つことになり、どこか腰の据わらない印象が残る演奏でした。正直、やり慣れた曲だから舐めてかかり、リハ不足なのではと感じました。LSOも年に何回かはこういう集中力に欠けた演奏をやらかしちゃうので、まあそこがカワイイと言えないこともないですが、さらに今日は管打楽器の各パートが序列を入れ替えていたようで、少なくともトランペット、ホルン、ティンパニはプリンシパルがファーストを取らず、他の奏者に譲っていたのでそれもあったのかも。
演奏がそんなんだったからことさら気に障ったのかも知れませんが、お客もダメダメで、演奏中にバサバサっとプログラムなどを落とす人が後を絶たず、第1楽章終了直後にはブラックベリーのアラーム音が響き渡るし、これでは集中しろというほうが、無理。それでも腐ってもLSOですから、最後の強奏になるとブラスなどもさすがに馬力を発揮し、音圧で圧倒していました。終了後のやんやのスタンディングオベーションを見て、みんな一体何を聴いていたのかなーと、納得いかない気分のまま会場を後にしたのでした。
LSO/MTT/ウィリアムズ(p)/ワッツ(s):マーラー4番 ― 2012/05/27 23:59

2012.05.27 Barbican Hall (London)
Michael Tilson Thomas / London Symphony Orchestra
Llŷr Williams (P-1), Elizabeth Watts (S-2)
1. Beethoven: Piano Concerto No. 3
2. Mahler: Symphony No. 4
今年1月以来のMTTです。今日は待望のマーラーですが、よく考えたらMTTのマーラーを聴くのは実演、レコード通じて初めてかも。
まずはベートーヴェン。ソリストのブロンフマンがウイルス感染のため数日前にキャンセルとなり、急きょ代役で呼ばれたのはウェールズ出身のリル・ウィリアムズ。外見はちょっとおどおどしていて線が細そうでしたが、粒がくっきりと揃ったごまかしのないピアノで好感が持てました。重厚感や深刻さを匂わせない自然体キャラで、ベートーヴェンよりはモーツァルトが向いているのでは、と思いました。オケのほうはイントロの弦のフレーズからして早速丁寧に作り込んだ演奏で、客演ながらコントロールの上手さに感心することしきり。昼間の疲れもあって(子供の運動会があったので)、後半はちょっと意識が遠のいてしまいました。
メインのマーラー4番をロンドンで聴くのは5度目、LSOでは2度目です。ちょっと慌てて入ってしまった冒頭の鈴はフルートにきっちり合わせてリタルダンドし、鈴だけインテンポで残すという「時間の歪み効果」はなかったです。先ほどのベートーヴェンに引き続き、マーラーもまたニュアンスの極地のような演奏で、事細かに音楽の表情を作り上げていきます。弦のアンサンブル、ヴァイオリンソロ、各管楽器のソロ、フルートユニゾンのピッチ、どこをとってもとにかくオケが上手い!今更ながら参りました。弦楽器の配置が、1月の「幻想」では低弦を右に置くモダン配置でしたが、今日は対向配置に変え、第1・第2ヴァイオリンの掛け合いを効果的に際立たせていました。
コンマスのシモヴィッチはいつもの散切り坊ちゃんカットから髪を切り、バックに流すような大人っぽい髪型に変えていました。この人の雄弁でのめり込み型のヴァイオリンは、LSOのコンマスの中でも最近一番のお気に入りです。いつもにこやかで、他の団員との会話も多く、若いけどメンバーに信頼されているのを感じます。変則チューニングの2楽章のソロは、あえて軋む音でガリガリと弾き込んでいたのがユニークでした。
3楽章は一転してロマンチックにとうとうと語りかけるような演奏。一しきり盛り上がった後のか細くつぶやくような、それでいて彫りの濃い弦を聴いて、一瞬バーンスタインの顔がMTTにかぶりました。
要の終楽章、ワッツのソプラノはあまり女っぽさがなく、少年のあどけなさを思わせる無垢な美声。細やかな表現が好ましい余裕たっぷりの歌唱で、この曲を今まで聴いた中でもかなり上位にランク付けしたい好演でした。初めて聴く人かと思いきや、チェックしたら2年前の「ヴァレーズ360°」で聴いていました。備忘録を読み返してやっと思い出しましたが、文章を残してなければすっかり忘れていたところです。
Michael Tilson Thomas / London Symphony Orchestra
Llŷr Williams (P-1), Elizabeth Watts (S-2)
1. Beethoven: Piano Concerto No. 3
2. Mahler: Symphony No. 4
今年1月以来のMTTです。今日は待望のマーラーですが、よく考えたらMTTのマーラーを聴くのは実演、レコード通じて初めてかも。
まずはベートーヴェン。ソリストのブロンフマンがウイルス感染のため数日前にキャンセルとなり、急きょ代役で呼ばれたのはウェールズ出身のリル・ウィリアムズ。外見はちょっとおどおどしていて線が細そうでしたが、粒がくっきりと揃ったごまかしのないピアノで好感が持てました。重厚感や深刻さを匂わせない自然体キャラで、ベートーヴェンよりはモーツァルトが向いているのでは、と思いました。オケのほうはイントロの弦のフレーズからして早速丁寧に作り込んだ演奏で、客演ながらコントロールの上手さに感心することしきり。昼間の疲れもあって(子供の運動会があったので)、後半はちょっと意識が遠のいてしまいました。
メインのマーラー4番をロンドンで聴くのは5度目、LSOでは2度目です。ちょっと慌てて入ってしまった冒頭の鈴はフルートにきっちり合わせてリタルダンドし、鈴だけインテンポで残すという「時間の歪み効果」はなかったです。先ほどのベートーヴェンに引き続き、マーラーもまたニュアンスの極地のような演奏で、事細かに音楽の表情を作り上げていきます。弦のアンサンブル、ヴァイオリンソロ、各管楽器のソロ、フルートユニゾンのピッチ、どこをとってもとにかくオケが上手い!今更ながら参りました。弦楽器の配置が、1月の「幻想」では低弦を右に置くモダン配置でしたが、今日は対向配置に変え、第1・第2ヴァイオリンの掛け合いを効果的に際立たせていました。
コンマスのシモヴィッチはいつもの散切り坊ちゃんカットから髪を切り、バックに流すような大人っぽい髪型に変えていました。この人の雄弁でのめり込み型のヴァイオリンは、LSOのコンマスの中でも最近一番のお気に入りです。いつもにこやかで、他の団員との会話も多く、若いけどメンバーに信頼されているのを感じます。変則チューニングの2楽章のソロは、あえて軋む音でガリガリと弾き込んでいたのがユニークでした。
3楽章は一転してロマンチックにとうとうと語りかけるような演奏。一しきり盛り上がった後のか細くつぶやくような、それでいて彫りの濃い弦を聴いて、一瞬バーンスタインの顔がMTTにかぶりました。
要の終楽章、ワッツのソプラノはあまり女っぽさがなく、少年のあどけなさを思わせる無垢な美声。細やかな表現が好ましい余裕たっぷりの歌唱で、この曲を今まで聴いた中でもかなり上位にランク付けしたい好演でした。初めて聴く人かと思いきや、チェックしたら2年前の「ヴァレーズ360°」で聴いていました。備忘録を読み返してやっと思い出しましたが、文章を残してなければすっかり忘れていたところです。
LSO室内楽アンサンブル/ゲルギエフ:狐/兵士の物語 ― 2012/05/13 23:59
2012.05.13 Barbican Hall (London)
Valery Gergiev / LSO Chamber Ensemble
Alexander Timchenko (T-1), Dmitry Voropaev (T-1)
Andrey Serov (Bs-1), Ilya Bannik (Bs-1)
Simon Callow (Narrator-2)
1. Stravinsky: Renard
2. Stravinsky: The Soldier’s Tale
3日連続、今週4回目のバービカン。今日はLSOの室内楽アンサンブルで曲目も渋かったためか、サークル、バルコニーは閉鎖されていましたが、それでもストールにも空席が目立ちました。
今日の驚きは、すでにROHの人気者となったヴィットリオ・グリゴーロ君が聴きに来ていたことです。LSOとあまり接点がなさそうなので、意外でした。派手な顔立ちの女性、老紳士と連れ立ってE列に座っていましたが、どうも「狐」に出演した歌手の一人がお友達のご様子。休憩後には消えていたので先に帰ったのかと思いきや、終演後、お連れの人と一緒に駐車場で車に乗り込むところを見たので、別室でお友達と盛り上がっていたんでしょうか。
Valery Gergiev / LSO Chamber Ensemble
Alexander Timchenko (T-1), Dmitry Voropaev (T-1)
Andrey Serov (Bs-1), Ilya Bannik (Bs-1)
Simon Callow (Narrator-2)
1. Stravinsky: Renard
2. Stravinsky: The Soldier’s Tale
3日連続、今週4回目のバービカン。今日はLSOの室内楽アンサンブルで曲目も渋かったためか、サークル、バルコニーは閉鎖されていましたが、それでもストールにも空席が目立ちました。
今日の驚きは、すでにROHの人気者となったヴィットリオ・グリゴーロ君が聴きに来ていたことです。LSOとあまり接点がなさそうなので、意外でした。派手な顔立ちの女性、老紳士と連れ立ってE列に座っていましたが、どうも「狐」に出演した歌手の一人がお友達のご様子。休憩後には消えていたので先に帰ったのかと思いきや、終演後、お連れの人と一緒に駐車場で車に乗り込むところを見たので、別室でお友達と盛り上がっていたんでしょうか。
1曲目の「狐」は男声4人とツィンバロンを含む15人の小管弦楽による、一種のバレエ作品。15分くらいの短い曲です。今日は演奏会形式なので踊りは無し。ストーリーは、鶏が狐に襲われて食べられそうになるが、猫と山羊に助けを求めて狐を撃退する、という単純な話です。男声4人は各々登場キャラクターの鶏、狐、猫、山羊に割り当てられており、そういう先入観で見ると、歌手の皆さんの風貌がまさに各々のキャラクターそっくりに見えてきて、可笑しかったです。ほとんど始めて聴いたのですが(それがこの演奏会に来た理由でもあります)、聴きやすくて楽しい曲です。是非バレエでも見てみたいです。
左から鶏、狐、猫、山羊です。特に右端のバンニクは、まさに山羊(笑)。
メインは「兵士の物語」。ストラヴィンスキーの代表作でかなり有名かと思いますが、こちらも実は聴いたことがありませんでした。7名の奏者とナレーターによる、朗読・演劇・バレエを融合した舞台作品、とのことで、様式的にはごった煮ながらも、わかりやすくて極めて魅力的な音楽です。ブレーク無しで1時間の長丁場を全く飽きることなく楽しめました。ストーリーは、兵役から故郷に帰る途中のヴァイオリン弾きジョゼフが悪魔に騙されて楽器と本を交換し、道草を食っている間に故郷の婚約者は別の男と結婚、当てもなく旅に出たジョゼフは病床のお姫様を悪魔から取り返したヴァイオリンで癒し、手に手を取って城から出て行くが、国境を越えたとたんに悪魔の手に落ち地獄行き、というお話(朗読は早くて途中着いていけなかったので、あらすじは後で調べました)。サイモン・キャロウ(映画「アマデウス」でシカネーダー役の人)の熱演もさることながら、LSOのトップ奏者が集った七重奏は、まさに粒が際立った至高のアンサンブル。ヴァイオリンのシモヴィッチはいつものごとく音楽に全く身を委ね、本当に楽しそうに弾いているのが、見ているこちらも幸せな気分になってきます。トランペットのコッブは対照的にクールに澄ました顔で、難しいフレーズも一点のキズなく吹きこなしてました。めちゃめちゃ贅沢な「兵士の物語」だったんではないでしょうか。
メインは「兵士の物語」。ストラヴィンスキーの代表作でかなり有名かと思いますが、こちらも実は聴いたことがありませんでした。7名の奏者とナレーターによる、朗読・演劇・バレエを融合した舞台作品、とのことで、様式的にはごった煮ながらも、わかりやすくて極めて魅力的な音楽です。ブレーク無しで1時間の長丁場を全く飽きることなく楽しめました。ストーリーは、兵役から故郷に帰る途中のヴァイオリン弾きジョゼフが悪魔に騙されて楽器と本を交換し、道草を食っている間に故郷の婚約者は別の男と結婚、当てもなく旅に出たジョゼフは病床のお姫様を悪魔から取り返したヴァイオリンで癒し、手に手を取って城から出て行くが、国境を越えたとたんに悪魔の手に落ち地獄行き、というお話(朗読は早くて途中着いていけなかったので、あらすじは後で調べました)。サイモン・キャロウ(映画「アマデウス」でシカネーダー役の人)の熱演もさることながら、LSOのトップ奏者が集った七重奏は、まさに粒が際立った至高のアンサンブル。ヴァイオリンのシモヴィッチはいつものごとく音楽に全く身を委ね、本当に楽しそうに弾いているのが、見ているこちらも幸せな気分になってきます。トランペットのコッブは対照的にクールに澄ました顔で、難しいフレーズも一点のキズなく吹きこなしてました。めちゃめちゃ贅沢な「兵士の物語」だったんではないでしょうか。
ゲルギーさん、いつものように爪楊枝を掴んで繊細なんだか無骨なんだかよくわからない指揮をしていました。今日はさすがに最後の拍手の際も、自分は脇に立って終始奏者を称えていました。
トランペットのフィリップ・コッブを称えるゲルギーさん。
トランペットのフィリップ・コッブを称えるゲルギーさん。
LSO/ゲルギエフ/カヴァコス(vn):ストラヴィンスキー、開幕 ― 2012/05/11 23:59
2012.05.11 Barbican Hall (London)
Valery Gergiev / London Symphony Orchestra
London Symphony Chorus
Maud Millar (S-1), Chloë Treharne (Ms-1)
Allessandro Fisher (T-1), Sandy Martin (T-1)
Oskar Palmbald (Bs-1)
Leonidas Kavakos (Vn-2)
1. Stravinsky: Mass
2. Stravinsky: Violin Concerto in D major
3. Stravinsky: The Firebird – complete ballet
ゲルギエフとLSOが今シーズン取り組むテーマの一つ、ストラヴィンスキーのシリーズが今日から始まります。まず1曲目、初めて聴く「ミサ曲」は、10名のウインド・アンサンブルとコーラスという特異な編成ながら、キリエ、グローリア、クレド、サンクトゥス、アニュス・デイという基本要素はきっちり押さえた、たいへんコンパクトなミサ曲です。作風区分で言うと新古典主義時代の最後のほうで、伴奏は多少おどけた雰囲気も出てないことはないですが、全般的に端正にハーモニーが整えられた、いたって厳かで真面目な曲でした。
先日と同じくロンドンシンフォニーコーラスは勉強熱心、出番が終わっても「コーラス席」にそのまま座って次の曲を聴いていました。次のヴァイオリン協奏曲もバリバリ新古典主義時代の作品で、けっこうお気に入りの曲なのでよく聴いているんですが、CDはムローヴァのしか持ってなく、唯一実演で聴いたのもムローヴァだったので、他の人が弾くとどうなるのか興味津々でした。去年のプロムスで容貌の変わりぶりに驚いてしまったカヴァコスは、どうも長髪が気に入ったようで、今や無精髭ぼーぼーの完全なヲタクルック。漂う不潔感ではゲルギエフに負けていません(笑)。しかしヴァイオリンとなると話は別、やっぱりこの人は超盤石なテクニックでどんな曲でも余力を持って弾き切ります。特にこういった軽めの曲では、肩の力の入らなさが実にニクらしい。大らかであり男勝りにガツガツ弾くムローヴァとはひと味違った、男の余裕の美学が感じられて面白かったです。
Valery Gergiev / London Symphony Orchestra
London Symphony Chorus
Maud Millar (S-1), Chloë Treharne (Ms-1)
Allessandro Fisher (T-1), Sandy Martin (T-1)
Oskar Palmbald (Bs-1)
Leonidas Kavakos (Vn-2)
1. Stravinsky: Mass
2. Stravinsky: Violin Concerto in D major
3. Stravinsky: The Firebird – complete ballet
ゲルギエフとLSOが今シーズン取り組むテーマの一つ、ストラヴィンスキーのシリーズが今日から始まります。まず1曲目、初めて聴く「ミサ曲」は、10名のウインド・アンサンブルとコーラスという特異な編成ながら、キリエ、グローリア、クレド、サンクトゥス、アニュス・デイという基本要素はきっちり押さえた、たいへんコンパクトなミサ曲です。作風区分で言うと新古典主義時代の最後のほうで、伴奏は多少おどけた雰囲気も出てないことはないですが、全般的に端正にハーモニーが整えられた、いたって厳かで真面目な曲でした。
先日と同じくロンドンシンフォニーコーラスは勉強熱心、出番が終わっても「コーラス席」にそのまま座って次の曲を聴いていました。次のヴァイオリン協奏曲もバリバリ新古典主義時代の作品で、けっこうお気に入りの曲なのでよく聴いているんですが、CDはムローヴァのしか持ってなく、唯一実演で聴いたのもムローヴァだったので、他の人が弾くとどうなるのか興味津々でした。去年のプロムスで容貌の変わりぶりに驚いてしまったカヴァコスは、どうも長髪が気に入ったようで、今や無精髭ぼーぼーの完全なヲタクルック。漂う不潔感ではゲルギエフに負けていません(笑)。しかしヴァイオリンとなると話は別、やっぱりこの人は超盤石なテクニックでどんな曲でも余力を持って弾き切ります。特にこういった軽めの曲では、肩の力の入らなさが実にニクらしい。大らかであり男勝りにガツガツ弾くムローヴァとはひと味違った、男の余裕の美学が感じられて面白かったです。
ところでカヴァコスはこのところ3年連続でプロムスで見ていて、ブダペストのころも何度か見ているのですが、容貌の変容が面白いです。上の髪を伸ばしたヲタクルックは昨年のプロムスからです。
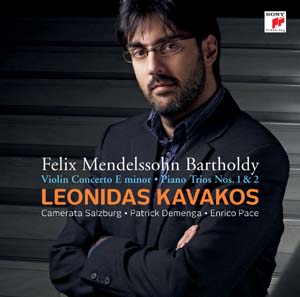
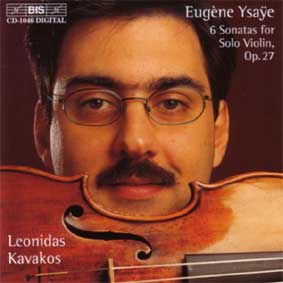
メインの「火の鳥」はゲルギーさんの得意中の得意、これがまた腰を抜かさんばかりの豪演に痺れました。躍動という言葉を忘れてしまったかのような先日のバルトークから一転、終始ヴィジュアルを喚起するダイナミックな演奏。「良いLSO」と「悪いLSO」があるとすれば、今日は全く「良いLSO」が全面に出ていました。デリケートな弦の弱音から強烈な大太鼓のアクセントまで、どのパートも集中力を切らさず最後まで緊張感を持続し、キズなし完璧というわけではなかったものの、是非とも録音していて欲しかった演奏でした(マイクがなかったのでしてないと思いますが)。クライマックスの「魔王カスチェイの凶悪な踊り」では最後にあまりに無茶な加速をして、それに応えるLSOの凄さよ。「火の鳥」は来シーズンのロイヤルバレエのプログラムに入っていますが、このオケと指揮者をこのままそっくりオペラハウスのオケピットに持って行きたい、と思ってしまいました。
かんとくさんのアイドル、チェロのミナ嬢は、入場のときにちらっと姿は見えたものの、後ろのほうだったので演奏中は全く見えず、残念…。理想のポジショニングはなかなか難しいです。
かんとくさんのアイドル、チェロのミナ嬢は、入場のときにちらっと姿は見えたものの、後ろのほうだったので演奏中は全く見えず、残念…。理想のポジショニングはなかなか難しいです。
























最近のコメント