俳句と打楽器が交差するミニマルな世界観:會田瑞樹(perc) ― 2025/03/15 23:59
2025.03.15 ムーブ町屋ムーブホール (東京)
俳句×打楽器:會田瑞樹パーカッションリサイタル
1. 會田瑞樹: 《一茶の俳句による打楽器のためのコンポジション》(新作)
2. 木下正道: 《旅心 〜種田山頭火の俳句による〜》(新作)
3. 佐原詩音: 《病牀六尺 〜四季めぐる 子規と夢みる 十四の句〜》(新作)
4. 国枝春恵: 《芭蕉の俳句における4つの時》(新作)
5. 松村禎三: 《ヴィブラフォーンのために 〜三橋鷹女の俳句によせて〜》(2002)
荒川区の2024年度支援事業「あらかわ文化イベント企画応援プロジェクト」で「俳句」をテーマにした企画公募により採択された演奏会の一つです。演奏に先立ち、會田氏自らこの企画の趣旨解説があり、自身が幼少のころから俳句に慣れ親しんでいたこと、上京後の初演奏会がこのムーブ町屋で荒川区とは縁が続いていること、日本現代音楽の黎明期を支えた指導者の池内友次郎が高浜虚子の息子にして自らも俳人であったことから、「荒川区にゆかりの俳句、俳人をモチーフに打楽器独奏用の新作を委嘱する」というアイデアを思いついたとのこと。
というわけで、本日のプログラムは出来立て新作4曲の初演のあと、松村禎三作品でシメるという、アプサラスの松村賞披露演奏会みたいな構成です。まず1曲目は會田氏自らによる小林一茶の有名な俳句7句を題材にした組曲。よく通る美声で俳句を読み上げ、スネアドラムとタム各種、ビブラフォン、仏具のような金属打楽器など各種打楽器を駆使して、スナッピーをギターのように指で弾いたり、電動歯ブラシを押し当てたりと小技を効かせて多彩な音色を奏でていました。俳句から想起される情景、情感を素直に表出した作品と見受けましたが、打楽器ソロという制約から、効果音を模した直接的な使い方が主になります。
続いて、「ゲージツ家クマさん」のような風貌の木下正道氏による、種田山頭火の俳句集「旅心」を題材にした作品。先ほどの一茶が「ザ・俳句」とも言える定型性と大衆性で日本人の耳に馴染むのに対し、定型も季語も無視した山頭火の自由律俳句に当てた音楽は1曲目とは全くアプローチが異なり、スネア、ロータム、ウッドブロック、タンバリンなど限られた小物打楽器をセットに固定して、わざと変な抑揚で読み上げた俳句に打楽器で合いの手を入れるような曲作りになっていました。山頭火の俳句がそもそもぶっ飛んでてわけわからんので、作曲の意図も非常に難解、しばし意識を失ってしまいました。後から突然思い出したのが、高校の国語の授業で習い非常に印象深かった「馬 軍港を内臓してゐる」という短い句。これも山頭火だったのかなと思って調べてみたら、「馬」は北川冬彦の有名な一行詩であって、山頭火の自由律俳句とは別ジャンルのようでした。と言われても、素人にはその違いがよくわかりません。
次は正岡子規の晩年の随筆「病牀六尺」をタイトルに据え、14の俳句をモチーフにした佐原詩音氏の作品。副題が五七五になっていて、「四季」と「子規」、「めぐる」と「夢みる」が韻を踏んでいてなかなか素敵です。六尺(約1.8m)の病床を模した煎餅布団がひかれ、寝っ転がって咳き込みながらシロフォンを叩いたり、スライドホイッスルで戯けて、鈴をかき鳴らし、なかなかにやりたい放題の多彩な曲でした。普通のオーケストラで「木琴」はマリンバではなくシロフォン、「鉄琴」はヴィブラフォンではなくグロッケンシュピールが定番というか常識ですが、それら4つを全て駆使する曲は珍しいです。長く結核を患い、34歳の若さで亡くなった子規ですが、その俳句や文筆はむしろ明るいものが多く、この作品もその情緒的なものを楽しげな音として捉えようとした様子が伺えます。
新作の最後は、大御所の国枝春恵氏による松尾芭蕉の有名な4つの俳句から想起される情況、感慨を音に還元した作品。いたずらに音色を試すようなことはせず、ヴィブラフォンを中心に各種銅鑼・ゴング類の金属打楽器と太鼓をはべらせた比較的シンプルな楽器構成。コントラバスの弓でヴィブラフォンを擦ったり、お経のように俳句を詠み上げたりと、多少のトリックを入れながらも、ミニマルな俳句の世界を隙間の多い音で表現したのはベテランのなせる技かと思いました。芭蕉をモチーフにした現代音楽は、昨年亡くなった湯浅譲二がいくつも作品を残しているので、恐れ多いと最初は断ったそうですが、これはこれで一つの世界観として成功しているのではないでしょうか。と言いながら、自分も実はその湯浅譲二作品を一つも聴いたことがないので、単なる素人の感想です。
演奏会のトリを飾るのは、俳句と打楽器ということでこの曲は欠かせなかったのであろう、松村禎三「ヴィブラフォーンのために」。この曲を聴くのは第1回アプサラス演奏会で初めて聴いて以来になりますが、會田氏も学生時代、まさに同じ日のアプサラス演奏会で師匠の吉原すみれさんの演奏を聴いて感銘を受け、自身の演奏家デビューにこの曲を選ぶくらいに惚れ込んだということです。ここまでの新作群と違ってヴィブラフォンだけと向き合い、完全暗譜で臨んだ渾身の演奏は、とても丁寧で、かつ共感が伝わるものでした。曲としては多分かなり難解な部類になり、モチーフの俳句がいかなるロジックで目の前の音楽に繋がるのか、2回聴いたくらいでは全く理解が追いつきませんが、あれだけ思い入れたっぷりに演奏されると、なんだかわからないけど奏者の心は十分に響いてきます。また、前回聴いたときと同じ感想になりますが、この音響空間の圧巻の迫力は、レコーディングには決して収まらず、その場でライブ体験しないと絶対に感じ取れないものだと思いましたので、今回再びこの曲が聴けたのはたいへん得難い機会でした。
マテウス/読響/ピーター・アースキン(ds):打楽器ドンパチを上手にさばいたエル・システマの新星 ― 2017/12/02 23:59
2017.12.02 東京芸術劇場コンサートホール (東京)
Diego Matheuz / 読売日本交響楽団
Peter Erskine (drums-2)
1. バーンスタイン: 「キャンディード」序曲
2. ターネジ: ドラムス協奏曲「アースキン」(日本初演)
3. ガーシュイン: パリのアメリカ人
4. ラヴェル: ボレロ
ちょうど1年前の今シーズンプログラムの発表から、ずっと楽しみにしていたコンサートです。5月には前哨戦としてコットンクラブにピーター・アースキン・ニュートリオのライブも見に行きました。ステージ奥の一番高いところに置かれたTAMAのドラムセットは多分そのときと同じものですが、メロタムとスプラッシュシンバルが増えて、若干フュージョン仕様になっているような。キックくらいはマイクで拾っているでしょうが、他は特にマイクやピックアップをセットしているようには見えませんでした。
ディエゴ・マテウスはベネズエラの有名なエル・システマ出身で、N響やサイトウキネンには過去何度か客演していますが、読響はこれが初登場とのこと。振り姿もサマになる、いかにもラテン系の若いイケメンで、まずは小手調べと披露した明るく快活な「キャンディード」序曲。モタらず、ノリが良く、この前のめりな指揮にオケがちゃんとついて行っているのが良い意味で予想を裏切り、なかなかの統率力をいきなりさらっと見せました。
続く「ドラムセットとオーケストラのための協奏曲《アースキン》」は2013年にピーター・アースキンのために作曲された作品。3本のサックスに大量の打楽器を含む大編成オケと、もちろんドラムセット、さらにエレキベース(意外と地味でしたが)まであり、ステージ上はお祭りの賑やかさです。作曲者のターネジは、前にも聞いた名前だなと思ったら、私は見に行けませんでしたが、2011年に英国ロイヤルオペラでの初演が物議を醸した「アンナ・ニコル」の作者でした。4つの楽章はそれぞれ以下のような表題があり、1は娘さんと息子さん、2は奥さん(ムツコさん)の名前から由来しています。
1. Maya and Taichi’s Stomp(マヤとタイチの刻印)
2. Mutsy’s Habanera(ムッツィーのハバネラ)
3. Erskine’s Blues(アースキンのブルース)
4. Fugal Frenzy(フーガの熱狂)
1回しか聴いていない印象としては、曲がちょっと固いかなと。確かに、ドラムセット以外にも打楽器満載で、ラテンやブルースのリズムを取り入れ、派手な色彩の曲に仕上がっていますが、バーンスタインのように突き抜けた明るさがなく、どことなく影が見えます。また、ドラムの取り扱いが思ったほど協奏的ではなくて、普通にドラムソロです。アースキンはさすがに上手いし、安定したリズム感はさすがですが、インプロヴィゼーションの要素がほとんど感じられず、やはりクラシックの舞台では「よそ行き顔」なんだなと感じてしまいました。嫌いなほうではないのですが、単なる「打楽器の多い曲」という印象で、期待したスリリングな「協奏曲」とはちょっと違いました。またやる機会があれば、是非聴きたいと思います。
後半戦は、管楽器のトップには試練の選曲が続きます。2曲とも1928年に作曲、初演されたという「繋がり」がミソ。「パリのアメリカ人」の実演は5年ぶりに聴きますが、管楽器のソロが粒ぞろいで驚きました。日本のオケで、ソロの妙技に感心する日が来ようとは。マテウスの指揮も全体を見通したもので、散漫になりがちなこの曲の流れを上手くまとめていました。ただし、ジャジーなスイング感はイマイチ。ラテンの人がジャズも得意とは限りません。
「ボレロ」の実演を聴くのはさらに久々で、7年ぶりでした。「ボレロ」が入っていると名曲寄せ集めプログラムになってしまうことが多いから、あえて避けてきた結果とも言えます。ここでも管のソロはそれぞれ敢闘賞をあげたいくらいのがんばりで(まあ、トロンボーンがちょっとコケたのはご愛嬌)、世界の一流オケが安全運転で演奏するよりも、かえって熱気があり良かったのではと思います。マテウスはこの曲でも若さに似合わぬ老獪さを発揮し、クレッシェンドを適切にコントロール。バランス感覚に優れている指揮者と思いました。このエル・システマの新星は、あくまで明るいラテン系のキャラですが、実力は本物だと確信しました。今後の活躍に期待です。
ピーター・アースキン・ニュー・トリオ+1@コットンクラブ ― 2017/05/10 23:59
2017.05.10 コットンクラブ (東京)
PETER ERSKINE NEW TRIO + 1
Peter Erskine (ds), Vardan Ovsepian (p), Damian Erskine (b), Aaron Serfaty (per)
そんなにたくさん聴いてきたわけじゃないけど、ピーター・アースキンのドラミングスタイルは、何を聴いても引き出しの多さに圧倒され、とても真似したり目指したりする気にならないので、正直好みではありませんでした。従って生で見る機会も今までなかったのですが、12月の読響演奏会でドラム協奏曲のソリストとして出演することが判明し、これは是非見に行かねばと楽しみにしていたところ、それに先立ってジャズトリオでの来日もあるということで、もう今年はピーター・アースキン・イヤーで行くしかないと、前哨戦として聴いてみました。
ステージ上のドラムセットは、シズルシンバルやペダル付きのカバサがちょっと目を引きますが、あとはワンタム、ツーフロアのいたってオーソドックスなジャズドラムセット。その横のパーカッションも、コンガ、ボンゴ、あと小物という感じで、スパイラルシンバルが珍しいくらい。さてトリオはドラム、ピアノ、エレキベースという構成で、今回はプラスワンとしてパーカッションが加わります。まあでも、パーカスは正直なくても困らない程度の存在感でした。甥っ子のベースを初め、ピーター以外は皆息子というよりむしろ孫に近いような若手を集め、「アースキン翁の音楽道場」といった趣きの朗らかさが漂っていました。若い3人はピーターを頼り切っている感じのバンドで、スリリングさはあまりなかったのが不満ですが、その中でもピアノは自身の作曲では時々エキセントリックな独特の曲調を覗かせて、良い味を出していました。
さて肝心のピーター・アースキンのドラムは、小技系かと思いきや、意外とラウド系。シンプルに粒のそろったビートを安定したタイム感で叩き出す、オーソドックスな正にお手本ドラム。バラードを含めリズミカルな曲ばかりで、16以外のありとあらゆるリズムのサンプルを聴かされた気分で、そのどれもが基本に忠実でありながら、やっぱり引き出しの多さは別格。ハメを外すことはなかったですが、リムショットしながら肘でスネアのヘッドを押してチューニングをグリッサンド気味に下げるというよくわからない裏技を披露する茶目っ気もあり。あらためて、凄い人でした。アコースティックなドラムの醍醐味を十二分に堪能させてもらいました。
(後で調べたら、ピーター・アースキン62歳、ヴァルダン・オヴセピアン41歳で、孫というほどの年齢差はないんですね、すんません…)
PETER ERSKINE NEW TRIO + 1
Peter Erskine (ds), Vardan Ovsepian (p), Damian Erskine (b), Aaron Serfaty (per)
そんなにたくさん聴いてきたわけじゃないけど、ピーター・アースキンのドラミングスタイルは、何を聴いても引き出しの多さに圧倒され、とても真似したり目指したりする気にならないので、正直好みではありませんでした。従って生で見る機会も今までなかったのですが、12月の読響演奏会でドラム協奏曲のソリストとして出演することが判明し、これは是非見に行かねばと楽しみにしていたところ、それに先立ってジャズトリオでの来日もあるということで、もう今年はピーター・アースキン・イヤーで行くしかないと、前哨戦として聴いてみました。
ステージ上のドラムセットは、シズルシンバルやペダル付きのカバサがちょっと目を引きますが、あとはワンタム、ツーフロアのいたってオーソドックスなジャズドラムセット。その横のパーカッションも、コンガ、ボンゴ、あと小物という感じで、スパイラルシンバルが珍しいくらい。さてトリオはドラム、ピアノ、エレキベースという構成で、今回はプラスワンとしてパーカッションが加わります。まあでも、パーカスは正直なくても困らない程度の存在感でした。甥っ子のベースを初め、ピーター以外は皆息子というよりむしろ孫に近いような若手を集め、「アースキン翁の音楽道場」といった趣きの朗らかさが漂っていました。若い3人はピーターを頼り切っている感じのバンドで、スリリングさはあまりなかったのが不満ですが、その中でもピアノは自身の作曲では時々エキセントリックな独特の曲調を覗かせて、良い味を出していました。
さて肝心のピーター・アースキンのドラムは、小技系かと思いきや、意外とラウド系。シンプルに粒のそろったビートを安定したタイム感で叩き出す、オーソドックスな正にお手本ドラム。バラードを含めリズミカルな曲ばかりで、16以外のありとあらゆるリズムのサンプルを聴かされた気分で、そのどれもが基本に忠実でありながら、やっぱり引き出しの多さは別格。ハメを外すことはなかったですが、リムショットしながら肘でスネアのヘッドを押してチューニングをグリッサンド気味に下げるというよくわからない裏技を披露する茶目っ気もあり。あらためて、凄い人でした。アコースティックなドラムの醍醐味を十二分に堪能させてもらいました。
(後で調べたら、ピーター・アースキン62歳、ヴァルダン・オヴセピアン41歳で、孫というほどの年齢差はないんですね、すんません…)
Hughes/Thrall ― 2010/05/28 06:11
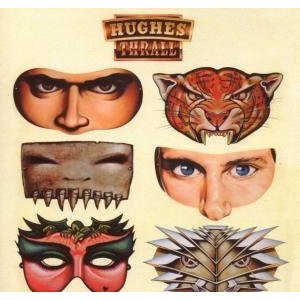
知る人ぞ知るハードロックの名盤「Hughes/Thrall」がリマスターで、しかもボーナストラック付きで出ているのを先月たまたま発見、ついポチってしまいました。初出は1982年、Best Hit USAでシングルカットのThe Look In Your Eyeを聴いてツボにはまり、LPレコードをそれこそすり切れるほど聴きたおしました。
CDの時代になってから(国内盤はもちろんないので)輸入CDをずいぶん探しましたが見つからず、1992年の学生のころ、初ヨーロッパ旅行の際にロンドンPccadilly Circusの今は亡きTower Recordで見つけたときの喜びといったら!Amazonなんか影も形もないころの話です。というわけで、このアルバムを買うのはこれで3回目ということになりますが、それがまたロンドンというのがなかなか感慨深いです。
あらためて聴いて、元々CDもそれほど音が悪かったわけではないのでリマスターで劇的に変わった感じはしませんでしたが、やっぱり素晴らしいのは何はともあれ内容で、何度聴いても一点の曇りもなく隅から隅までカッコいい!リリース当時、なぜ売れなかったのか全く不思議でなりません。GlennのボーカルとPatのギターが凄いのはもちろんのこと、ドラムが、言ってしまえばヘタウマ系ですが微妙なタメが何ともいい味を出していて、ヘビメタでもファンクでもR&Rでもない、危うくもユニークなカッコよさで大好きでした。LPでドラマーとしてクレジットされていたのは当時新人のFrankie Banali(後にQuiet Riotに加入、新人とは言えGlennと同い年なので当時からもうオジンですが)だけだったような気がするのでずっとそう思いこんでいたのですが、あらためてこのリマスターCDのブックレットを見てみると、他にもGary Ferguson、Gary Mallaberの名前があります。どの曲が誰のプレイかは書いてませんが(ご存知の方は是非教えてください)、プロデュースの素晴らしい統一感のおかげでドラマーが複数いるのを全然感じさせませんでした。
なお、幻のセカンドアルバム用に録音したと言われるボーナストラックは、ファースト命なだけに、ちょっと微妙。やっぱり疾走感や勢いが後退し、加齢臭をどうしても感じてしまいます…。
CDの時代になってから(国内盤はもちろんないので)輸入CDをずいぶん探しましたが見つからず、1992年の学生のころ、初ヨーロッパ旅行の際にロンドンPccadilly Circusの今は亡きTower Recordで見つけたときの喜びといったら!Amazonなんか影も形もないころの話です。というわけで、このアルバムを買うのはこれで3回目ということになりますが、それがまたロンドンというのがなかなか感慨深いです。
あらためて聴いて、元々CDもそれほど音が悪かったわけではないのでリマスターで劇的に変わった感じはしませんでしたが、やっぱり素晴らしいのは何はともあれ内容で、何度聴いても一点の曇りもなく隅から隅までカッコいい!リリース当時、なぜ売れなかったのか全く不思議でなりません。GlennのボーカルとPatのギターが凄いのはもちろんのこと、ドラムが、言ってしまえばヘタウマ系ですが微妙なタメが何ともいい味を出していて、ヘビメタでもファンクでもR&Rでもない、危うくもユニークなカッコよさで大好きでした。LPでドラマーとしてクレジットされていたのは当時新人のFrankie Banali(後にQuiet Riotに加入、新人とは言えGlennと同い年なので当時からもうオジンですが)だけだったような気がするのでずっとそう思いこんでいたのですが、あらためてこのリマスターCDのブックレットを見てみると、他にもGary Ferguson、Gary Mallaberの名前があります。どの曲が誰のプレイかは書いてませんが(ご存知の方は是非教えてください)、プロデュースの素晴らしい統一感のおかげでドラマーが複数いるのを全然感じさせませんでした。
なお、幻のセカンドアルバム用に録音したと言われるボーナストラックは、ファースト命なだけに、ちょっと微妙。やっぱり疾走感や勢いが後退し、加齢臭をどうしても感じてしまいます…。
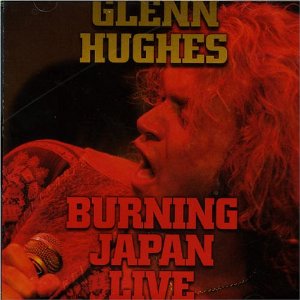
Amazon.co.ukでついでに見つけたGlenn Hughesのクラブチッタ川崎での1994年のライブを収めた「Burning Japan Live」も一緒にゲット。いきなりBurnでぶちかまし、Hughes/ThrallやDeep Purpleの曲もたくさんやってくれてて、こんなライブをこっそり?やってたなんて全然知りませんでした。まあ、研究室に寝泊まりしてた1994年当時のことを思い出せば、ライブ情報を拾って、チケット買って、聴きにいってたかというと、そんな余裕はなかったかも…。
HUGHES/THRALL (1982)
1. I Got Your Number
2. The Look In Your Eye
3. Beg, Borrow Or Steal
4. Where Did The Time Go
5. Muscle And Blood
6. Hold Out Your Life
7. Who Will You Run To
8. Coast To Coast
9. First Step Of Love
10. Still The Night (Bonus)
11. Love Don't Come Easy (Bonus)
Musicians:
Glenn Hughes: Vocals, Bass
Pat Thrall: Guitar, Guitar Synthesizer
Frankie Banali: Drums
Gary Ferguson: Drums
Gary Mallaber: Drums
Peter Schless: Keyboards



最近のコメント